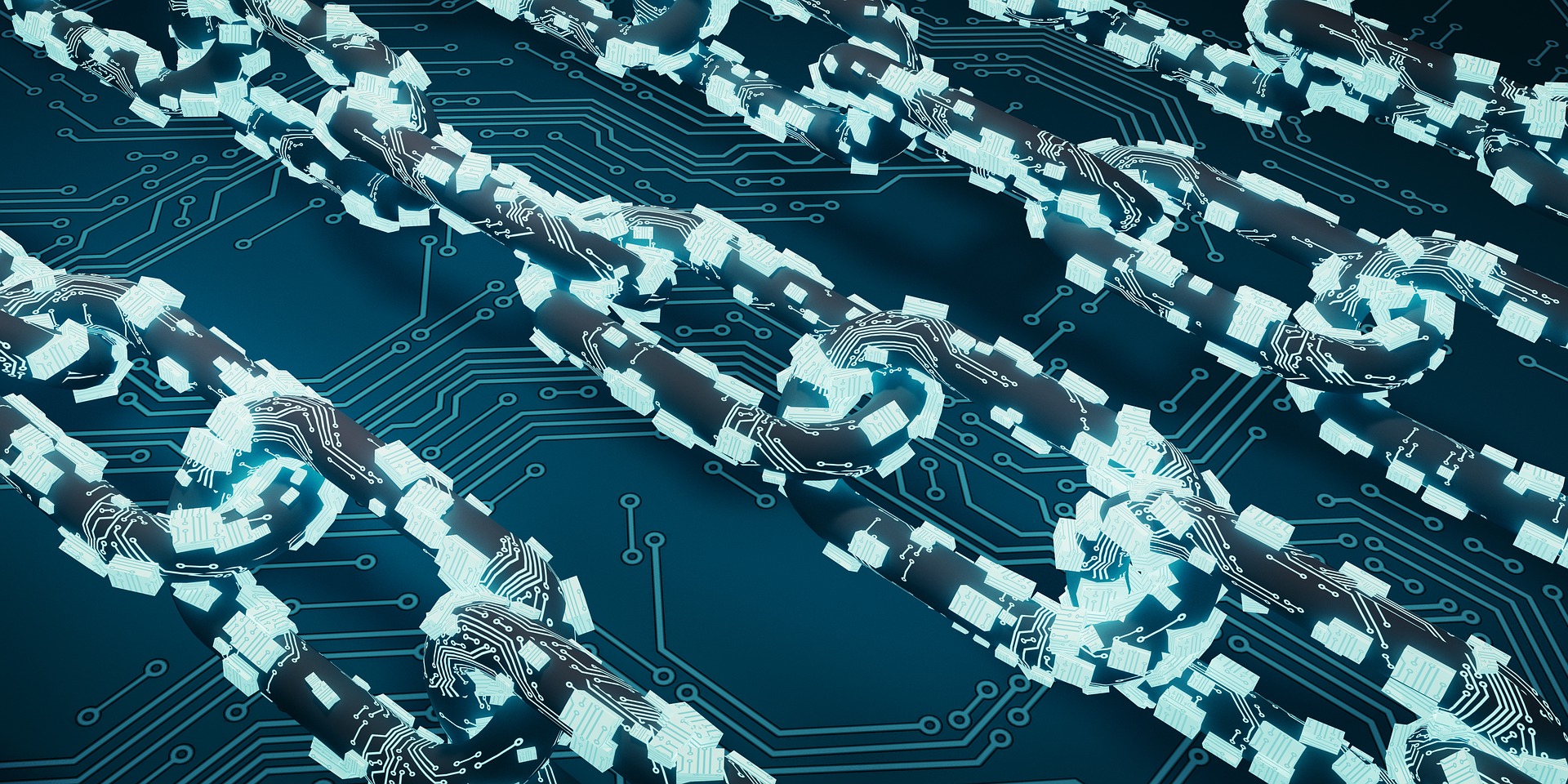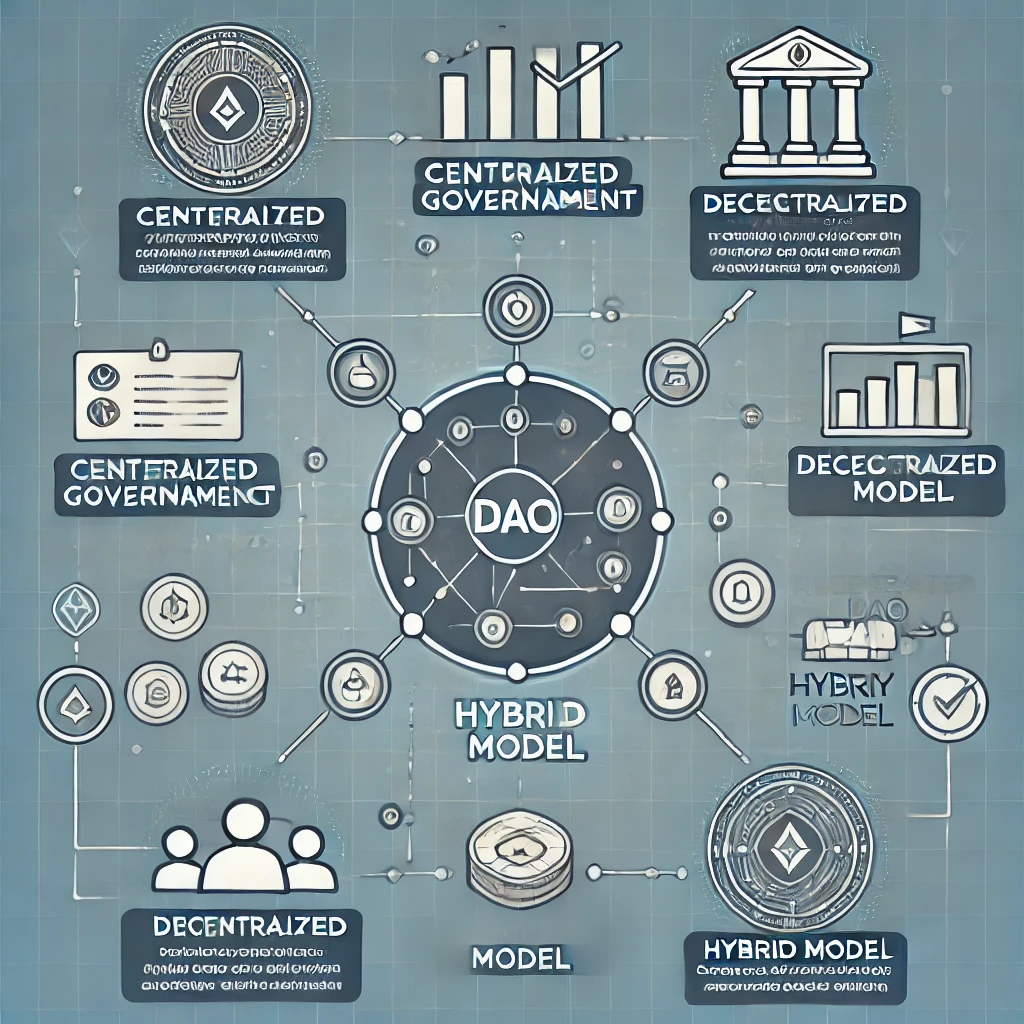1. オフショア開発拠点を持つことの重要性
近年、企業が競争力を維持しながら迅速なプロダクト開発を行うためには、優れた技術力を持つリソースを適切なコストで確保することが求められています。当社は、戦略提言だけでなく開発まで一気通貫でのサービスを低価格で提供することを強みとしています。その実現のために、オフショア開発の活用は極めて有効な手段となります。
特にベトナムは、優秀なエンジニアが多く、開発コストの面でも非常に魅力的な市場です。さらに、日本との時差がほぼなく、円滑なコミュニケーションが可能な点も大きなメリットです。こうした背景から、当社ではベトナムに自社のオフショア開発拠点を設立することを決定しました。
2. 自社オフショア拠点を持つメリット
① 潤沢なリソースの確保
外部のオフショア開発会社を利用する場合、他社とのリソース競争が発生し、必要な人材を確保するのが難しくなることがあります。しかし、自社拠点を持つことで、プロジェクトの規模やスケジュールに応じて柔軟にリソースを割り当てることが可能になります。
② 技術力の向上とナレッジの蓄積
外部ベンダーに依存すると、プロジェクトごとに異なる技術スタックや開発手法が用いられることがあり、ナレッジの蓄積が困難です。一方、自社の開発拠点を持つことで、独自の開発フレームワークや標準化されたプロセスを確立し、継続的に技術力を向上させることができます。
③ コストパフォーマンスの最適化
オフショア開発は低コストで優秀なエンジニアを確保できる一方で、ブローカーを介した場合は中間マージンが発生します。自社で開発拠点を持つことで、余計なコストを抑えながら、より高品質な開発を実現できます。
④ クライアントへの高付加価値提供
戦略提言から開発までを一貫して提供する当社のモデルにおいて、自社オフショア拠点を持つことは、クライアントに対するスピーディな対応と高品質な開発を実現する鍵となります。コストを抑えつつ、フレキシブルな開発体制を構築できるため、より競争力のあるサービスを提供できます。
3. 将来的な展望:日系大企業への売却も視野に
ベトナムにおける開発拠点を成長させることで、当社にとっての中長期的な出口戦略も多様化します。例えば、一定規模まで育成した開発会社を、技術力の強化を狙う日系大企業に売却することで、大きなキャピタルゲインを得る可能性もあります。
実際、近年では日本企業がオフショア開発の内製化を進める動きが活発化しており、優秀な開発リソースを持つベトナム企業は非常に魅力的な買収対象となっています。将来的に、当社が築いた開発拠点を「売却可能な資産」として活用できるよう、成長戦略を描いていきます。
4. まとめ
ベトナムに自社のオフショア開発拠点を設立することで、当社の一気通貫サービスの強化、リソースの確保、コストパフォーマンスの最適化、そして将来的な企業価値向上を実現できます。単なるコスト削減のためのオフショア活用ではなく、企業の成長戦略の一環としてオフショア拠点を活用し、事業の発展を加速させていきます。
今後の展開としては、ベトナムの現地パートナーとの連携、優秀なエンジニアの採用・育成、開発プロセスの標準化を進めながら、クライアント企業に対してさらなる価値を提供していきます。